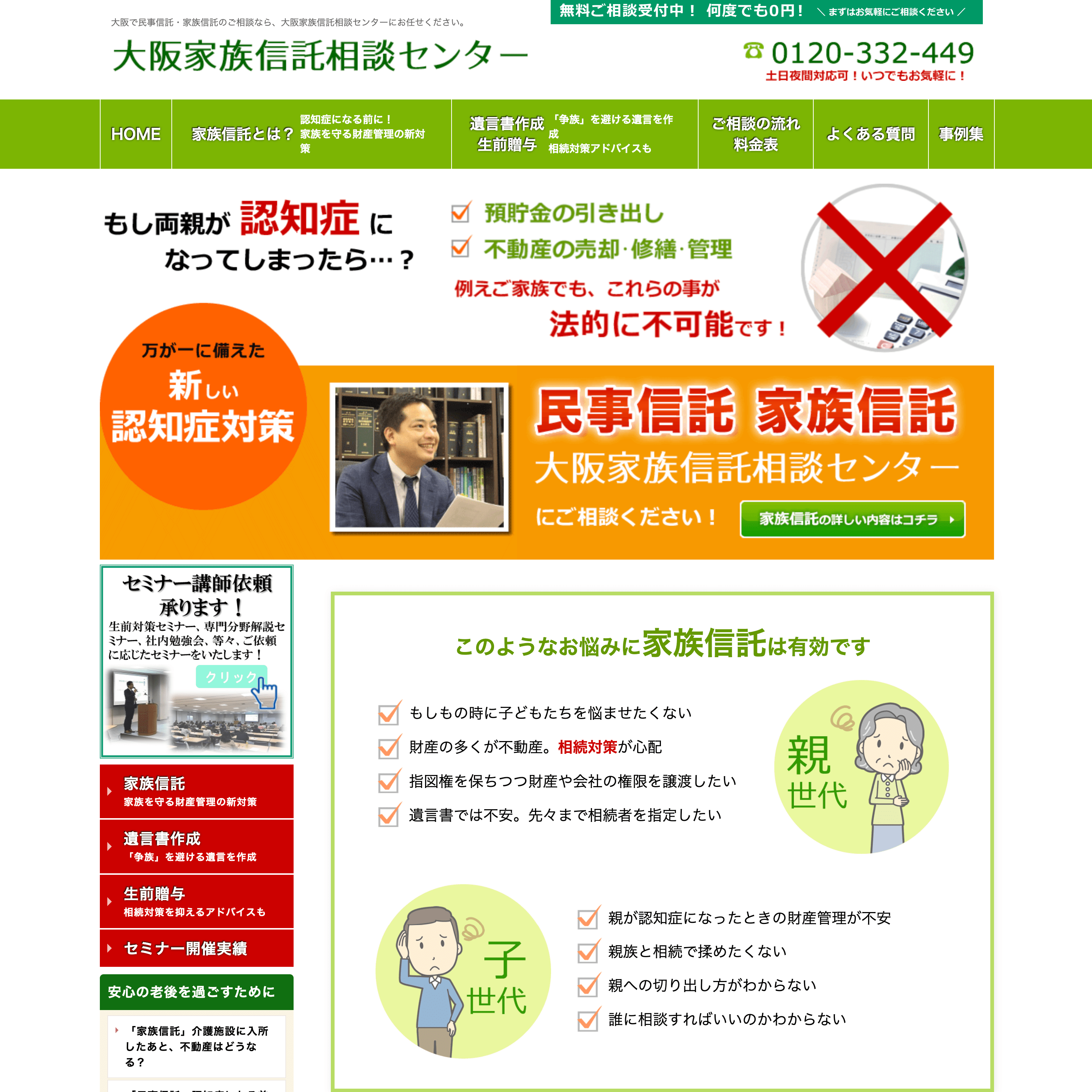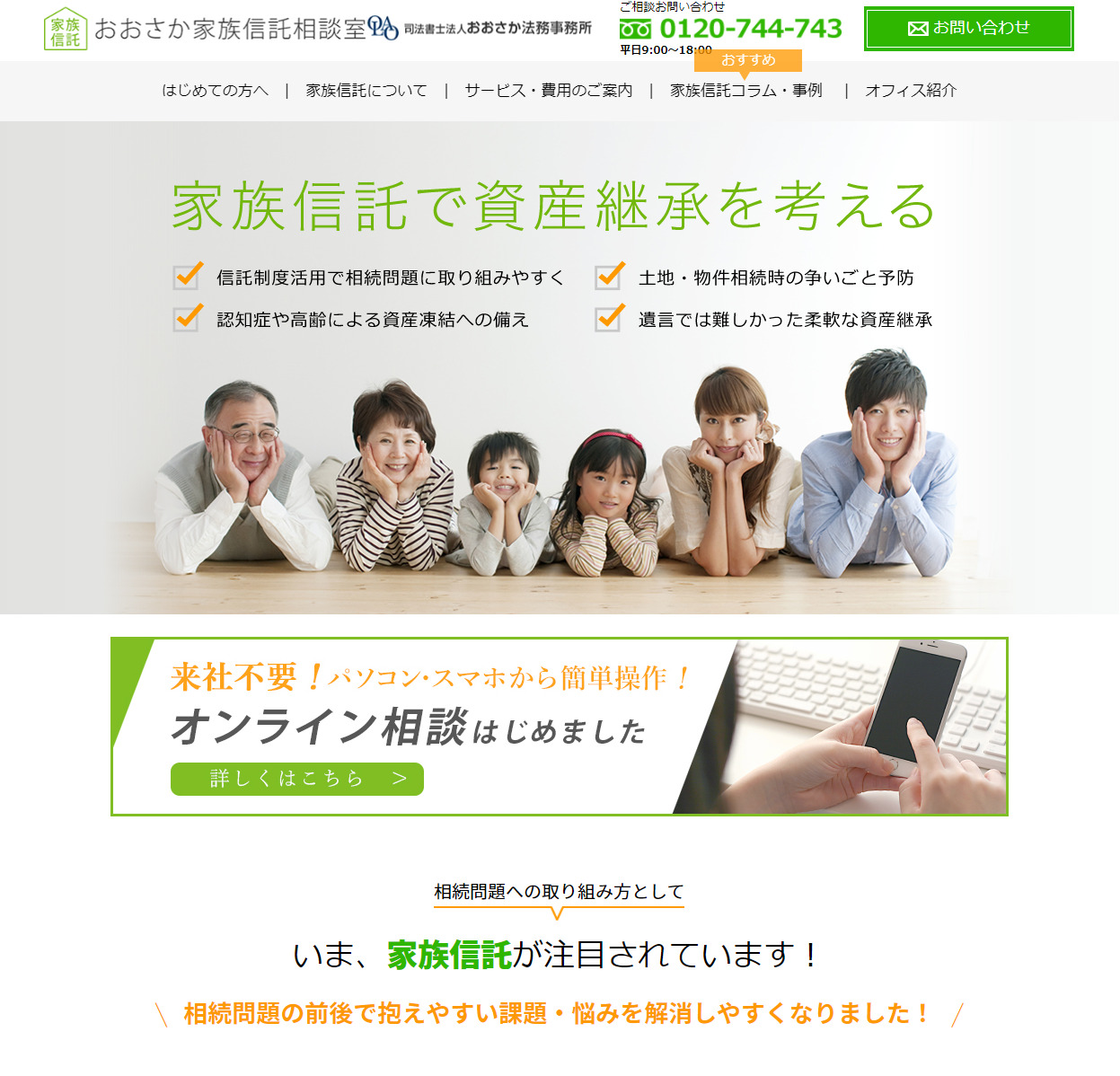家族信託を利用する際の手続きの流れを解説

家族信託を利用したいけど手続きの流れがわからない、家族信託に必要な書類がわからず困っているといった悩みを抱えていませんか?この記事では、家族信託前に決定しておきたいポイントや家族信託に必要な書類、手続きの流れを紹介します。本記事の内容が、家族信託を検討している方の参考になれば幸いです。
家族信託利用前に決めておくべきポイント
家族信託を利用する際には、家族間であらかじめ重要なポイントの話し合いと決定が不可欠です。
以下に主要なポイントを説明します。
利用目的を明確にする
まず、家族信託を利用する目的の明確化が第一のステップです。
家庭の状況や家族構成、そして財産状況は各家庭で異なるため、それぞれに適した信託の目的設定が求められます。家族間で十分に話し合い、共通の目的を確認してから次のステップへ進みましょう。
信託対象とする財産を選定する
次に、信託の対象となる財産の選定が必要です。
信託の対象となり得るのは、現金、預金、株式などの有価証券、不動産などの財産です。どの財産を信託にするかは、家族全員が納得できるように十分な話し合いを行います。財産の管理や運用方法はは非常に重要な決定事項であり、慎重に審議する必要があります。
信託契約の内容を検討する
信託する財産が決まったら、契約内容について具体的に検討を始めます。
たとえば、誰を受託者にするか、誰を受益者にするか、信託の管理者をどうするか、そして信託の期間が終了した後の財産の処分をどうするかなどです。受託者は財産の管理や運用、処分を行う役割を担い、受益者はその利益を受け取る者です。
また、受託者管理人を任命するかどうかも考慮する必要があります。受託者管理人は、受託者が契約に従って財産を適切に管理しているかを監視する役割を果たします。
家族全員から同意を得る
さらに、信託契約の内容を決める際には、家族全員の理解と納得を得ることが重要です。
信託の内容が不明確であったり、家族間で不満が生じるような場合は再度話し合いを行い、できる限り全員が納得できる形への調整が望まれます。
家族信託の内容を正式な契約書に盛り込む
最後に、家族信託の内容を正式な契約書に盛り込む必要があります。
信託契約書は、信託財産と委託者や受託者個人の財産を明確に区別し、信託が適用される範囲を明確にします。家族信託における内容が記載された契約書により、信託契約の効力が適切に発揮されます。
家族信託に必要な書類
家族信託では、以下の基本的な書類の用意が求められます。
本人確認資料
まず、本人確認資料が必要です。
運転免許証やマイナンバーカードなどの、公的機関から発行された書類が該当します。
実印・印鑑証明書
本人確認資料に加えて、受託者と受益者の実印と印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は発行から3カ月以内であることが求められます。
信託対象の財産に関する資料
また、信託の対象となる財産に関する資料も準備する必要があります。
不動産を信託する場合は、不動産の登記事項証明書および不動産価格の証明に必要な固定資産税評価証明書や固定資産税課税明細書も必要です。さらに、家族関係を証明するための、戸籍謄抄本も必要です。
不動産登記手続きが必要な場合もある
次に、不動産を家族信託する場合には、不動産登記の手続きが必要です。
不動産登記の手続きでは、不動産の名義を委託者から受託者に変更する登記を申請します。登記を行うと、名義変更と同時に信託目録が作成され、信託内容が記録されます。
不動産登記に必要な書類としては、委託者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)、登記済証または登記識別情報、委託者の実印、運転免許証などの委託者と受託者の本人確認資料、受託者の住民票、受託者の認印などが挙げられます。
家族信託利用までの手続きの流れ
家族信託の手続きにはいくつかのステップがあり、それぞれをしっかりと理解し準備を進めることが大切です。
その大まかな流れを次に説明します。
家族間の合意形成
まず、最初のステップは家族間で信託内容についての話し合いを行い、合意を得ることです。
家族信託の目的が明確になると、家族信託手続きの出発点となります。家族信託は、認知症対策、財産の継承、障害を持つ子どもの将来をサポートするなど、さまざまな目的で利用されます。
重要なのは、委託者と受託者だけで全てを決めるのではなく、他の家族の意見も十分に聞くことです。他の家族の意見を無視して進めてしまうと、後になってトラブルに発展するリスクがあります。
信託契約書の作成
次のステップは、話し合いで決定した内容を基にした、信託契約書の作成です。
契約書の作成に際しては、できる限り具体的な表現を用いることが大切です。曖昧な表現が残ると、後に解釈の違いが生じ、財産管理に支障をきたす可能性があります。
また、信託契約書の作成にあたっては、司法書士や弁護士、税理士などの専門家への相談が推奨されます。作成した契約書は、公証役場で公正証書にすることが望ましいです。
財産の名義変更
契約書が完成したら、次のステップは財産の名義変更です。
名義変更の手続きは、財産の種類によって異なります。たとえば、信託財産に不動産が含まれている場合、法務局にて親から受託者である子への所有権移転登記を申請する必要があるので注意しましょう。
専用口座の開設
最後のステップは、財産管理専用口座の開設です。
信託財産に現金・預金が含まれる場合は、管理するための専用口座を開設し、信託財産をその口座に入金して管理します。専用口座を設けることで、信託財産と個人財産を明確に区別し、適切な管理が可能になります。
まとめ
家族信託の手続きは複雑に感じるかもしれませんが、順を追って理解すればスムーズな進行が可能です。まず、家族全員で信託の目的を明確にし、信託する財産や受託者を慎重に選定する過程が大切です。次に、信託契約書を具体的かつ正確に作成し、公正証書化の検討によりトラブルを未然に防ぎます。次に、財産の名義を適切に変更し、専用口座を開設して管理を開始します。一連のステップを踏むことで、家族信託の効果的な運用が実現し、家族の財産における安全な管理が可能です。家族全員の同意と専門家のサポートが、成功への鍵となります。
何度でも相談無料で安心できる相談先は…
-
 引用元:https://shine-kazokushintaku.com/
「一番親身な相続相談所でありたい」思いから何度でも無料相談の家族信託相談ひろば (シャイン司法書士法人・行政書士事務所)。料金も業界内で安いのが特徴で、相続に関する手続き費用をできるだけ抑えたいという方にもおすすめです!口コミ・評判もよく「一言一言に激励され、また、安心することができました。本当に感謝という言葉しかでてきません。(青太字)」などお願いして良かったと称賛する声が多く見受けられます。豊富な相続相談実績のあるプロフェッショナル集団なので遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなどなんでも相談でき、最適な相続対策を提案してもらえます。ぜひ一度HPをご覧ください♪
引用元:https://shine-kazokushintaku.com/
「一番親身な相続相談所でありたい」思いから何度でも無料相談の家族信託相談ひろば (シャイン司法書士法人・行政書士事務所)。料金も業界内で安いのが特徴で、相続に関する手続き費用をできるだけ抑えたいという方にもおすすめです!口コミ・評判もよく「一言一言に激励され、また、安心することができました。本当に感謝という言葉しかでてきません。(青太字)」などお願いして良かったと称賛する声が多く見受けられます。豊富な相続相談実績のあるプロフェッショナル集団なので遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなどなんでも相談でき、最適な相続対策を提案してもらえます。ぜひ一度HPをご覧ください♪